はじめに|「あっ、むせた…」そのとき焦らないために
食事介助の現場では、ふとしたタイミングで利用者さんが「むせてしまう」「喉に詰まらせる」ことがあります。
咳き込むだけで済むこともあれば、緊急対応が必要になることも。
この記事では、食事中によくあるトラブルへの正しい対処法と、事前にできる予防策を紹介します。
「いざというとき」に備えて、ぜひ一度目を通してみてください。
よく出てくる言葉の説明
- 嚥下(えんげ):食べ物や飲み物を口から喉、そして食道へと飲み込む動きのことです。
- 誤嚥(ごえん):食べ物や唾液が気管(息の通り道)に誤って入ってしまうこと。むせたり、肺炎の原因になることがあります。
- 窒息(ちっそく):喉や気道が詰まり、呼吸ができない状態になること。命にかかわる緊急事態です。
よくあるトラブルとその場の対応
- むせる(誤嚥)
声を出して咳ができるなら、咳を促しつつ見守る。
姿勢を少し前かがみにして、自然に吐き出せるようにする。
落ち着いたら、水分や食事を一旦中止し、経過観察を。 - 喉に詰まる(窒息)
咳も声も出ない、顔が赤くなる・苦しそうな様子。
→ 迷わず「背部叩打法」または「ハイムリック法」へ(後述)
→ 同時に、看護師へ速やかに連絡を行う。状態によっては救急要請が必要になることもあります。 - 嘔吐・意識低下
すぐに体を横にして、誤嚥や窒息を防ぐ。
→ 嘔吐物が気道に流れ込むのを防ぐため。仰向けのままだと、吐いたものを誤嚥しやすく、窒息や肺炎のリスクが高まります。
看護師に即時連絡、必要があれば救急要請。
窒息時の応急対応|図で見る2つの方法
背部叩打法(タッピング)
前かがみにして、肩甲骨の間を手のひらで強く数回叩くことで、詰まったものを出す方法です。

ハイムリック法(腹部突き上げ法)
喉に物が詰まって呼吸ができないとき、背後からみぞおちのあたりを突き上げる応急処置です。

※意識がない場合は、直ちに心肺蘇生を開始。
※妊婦や乳児には適用不可。別の対応が必要です。
トラブルを防ぐ!食事介助の5つの基本
- 正しい姿勢(背筋を伸ばし、足裏が床につくように)
- 一口量を少なく(大きすぎないよう調整)
- ペースはゆっくり(飲み込むのを確認してから次へ)
- 声かけで意識を保つ(「ゆっくり噛んでくださいね」など)
- 食事前に口腔・覚醒チェック(口の中や眠気をチェック)
食欲がない・口を開けない方への対応ポイント
- 体調の確認が最優先:
「今日はちょっと元気がないかも?」と感じたら、無理に食事を進めず慎重に。 - その日の変化を思い出してみる:
朝の様子、バイタル、排泄、レクリエーション…何か「いつもと違うこと」はなかったかを振り返る。
→ 異常が疑われるときは、無理に介助を続けないことが大切。 - 声かけは「責めず・焦らず・やさしく」:
「どうしましたか?」「今日はちょっとしんどいですか?」など、気持ちに寄り添う声かけを。 - タイミングをずらす・別の職員が試す:
職員との相性やタイミングで、すっと口を開けてくれることも。 - 好きなものから勧めてみる:
好物や食べやすいものから始めると、一口が入りやすくなることがある。
→ ただし、口に入っただけで安心せず、“嚥下できているか”をしっかり確認する。
→ 飲み込めていない状態で次を勧めると、誤嚥のリスクが高まる。 - 記録・報告を忘れずに:
食事量・拒否の様子・対応内容をしっかり記録。 - 継続する場合は管理栄養士・看護師と連携を:
とろみ剤や食形態の変更は、必ず専門職と相談のうえで行う。
たけのこの一言
「むせ」は誰にでも起こること。大切なのは、そのとき慌てず、落ち着いて対応できることです。
私も新人の頃、初めて窒息しかけた方に背部叩打をしたとき、手が震えました。
でも、“知っていた”からこそ動けた。
現場で働く皆さんが、安心して介助できるよう願っています。
合わせて読みたい
- 新人介護士さんへ|はじめての食事介助で気をつけたいこと
- “介助”と“自立支援”の違いに気づいた日|新人介護士 八琉木みなぎの成長日記
- 誤嚥性肺炎のリスクと予防法(準備中)
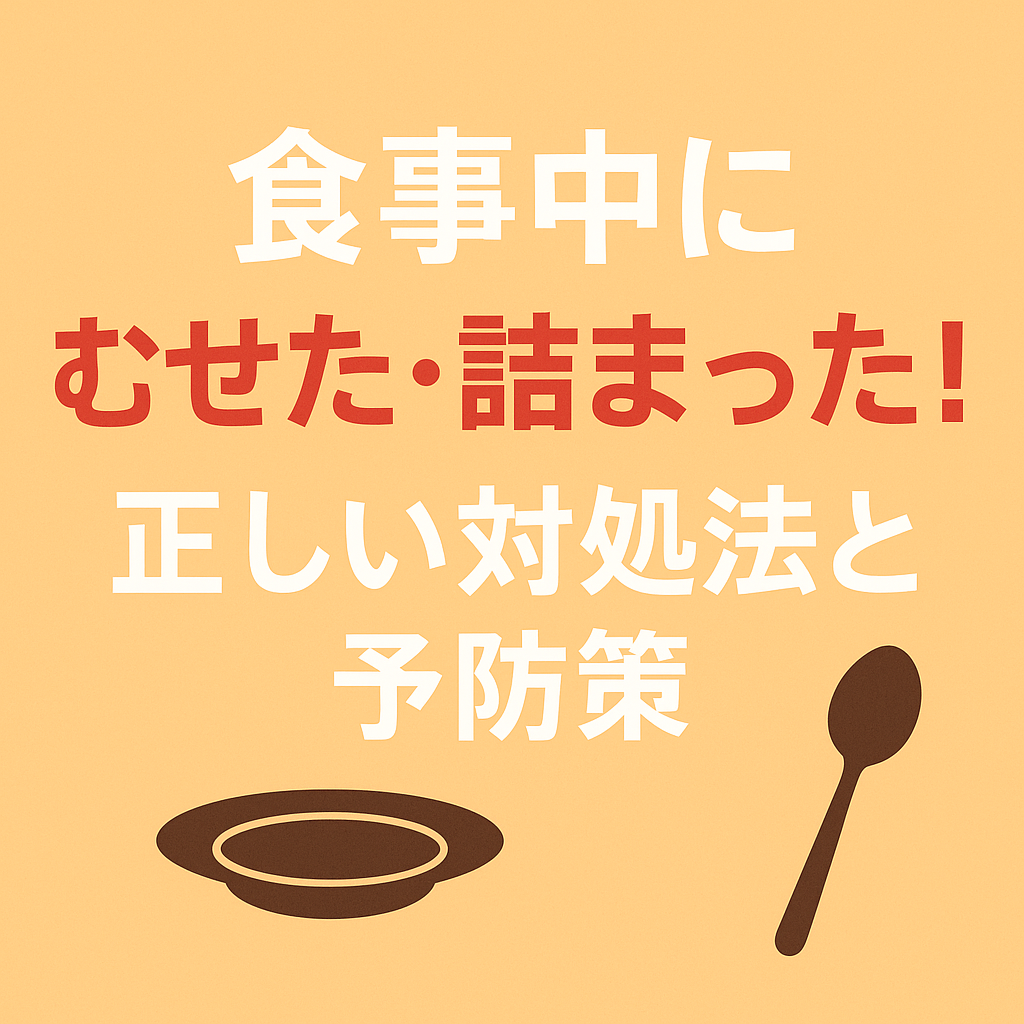

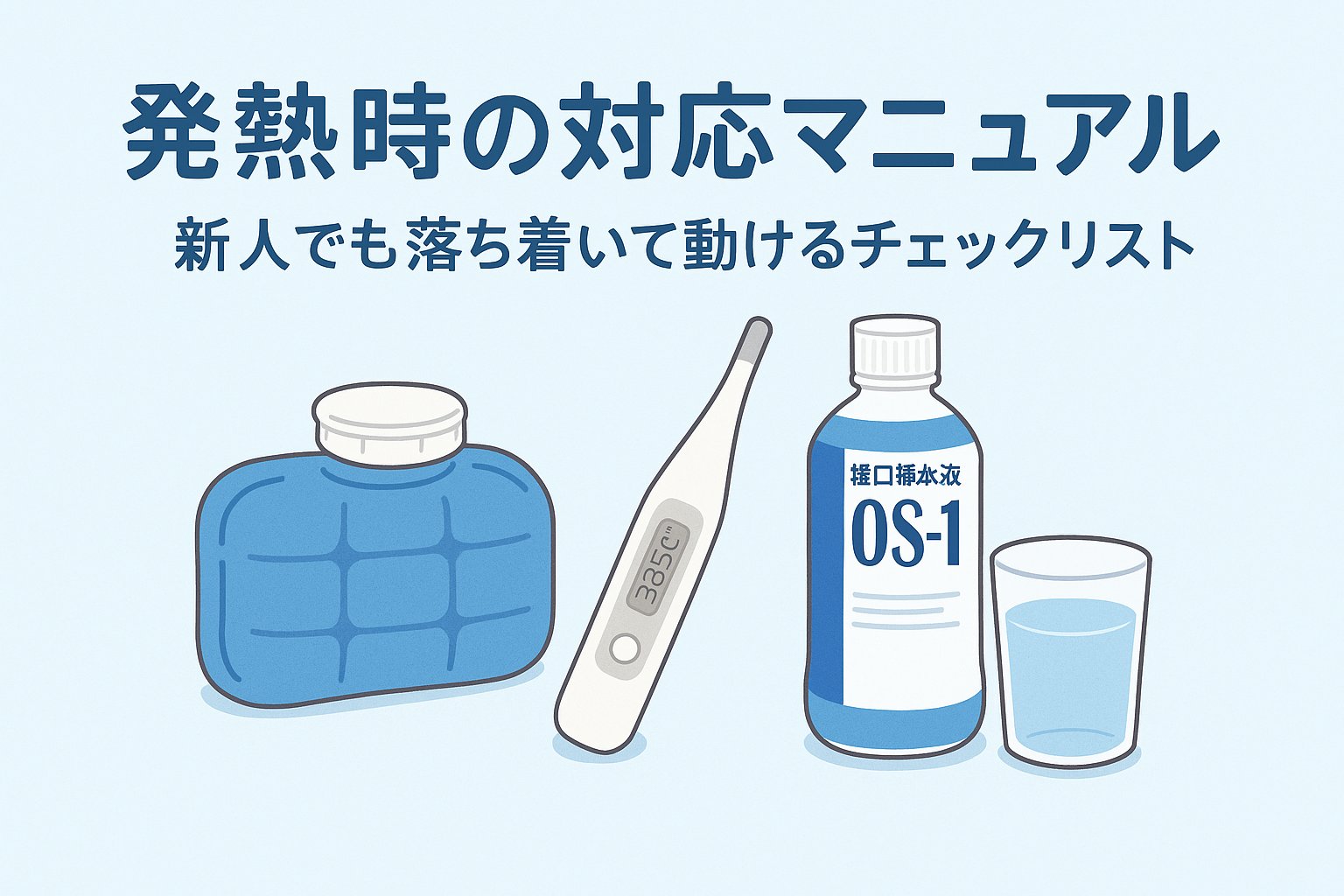
コメント