介護の現場で「食事介助」を初めて担当するとき、
「どこまで手伝えばいいんだろう」「この介助で本当にいいのかな」と、戸惑うことも多いと思います。
私自身も、新人のころはスプーンを持つ手が震えていました。
このページでは、食事介助の基本と注意点を、現場経験をふまえてやさしく解説します。
利用者さんの「自分で食べたい」気持ちを大切に、安心して取り組めるようサポートします。
食事介助とは?
食事介助は、ただ「口まで運ぶ」だけの仕事ではありません。
- 安全に食べられる姿勢を整える
- 食事しやすい環境をつくる
- 一口の量やタイミングを調整する
- 必要なら声かけや見守りでサポートする
つまり、「食べる」を支えるすべてが、食事介助です。
食事介助の基本的な流れ
- 声かけと説明
「○○さん、お食事の時間です。ご一緒させてくださいね」
いきなり介助に入らず、本人のペースに寄り添いましょう。 - 姿勢の確認
誤嚥を防ぐため、背もたれを少し起こす・足をしっかり床につける。
体を傾けないよう、クッションで支えるのも効果的です。 - 一口の量・スプーンの使い方
量は小さめ・やや平たくが基本。
スプーンは唇に触れたら待つ、自分から口を開けるまで押し込まない。 - 水分の提供タイミング
食べ物と食べ物のあいだや、嚥下が心配なときに。
とろみをつける必要がある場合もあります。
気をつけたいポイント
- むせ・誤嚥のリスクに注意
飲み込みが苦手な方にはとろみ食やソフト食が使われていることも。必ず確認しましょう。 - 「ごっくん」を確認してから次の一口
喉の動きや、飲み込む音をよく観察します。 - 片麻痺がある方は、麻痺のない側から介助
視認性が高まり、自分で食べようとする動作も促せます。 - むせたときは、すぐ再開しないこと
少し時間をおいて、再開する際はごく少量から慎重に。 - スプーンは“下から”、口元が見える位置で
利用者さんに「何を食べるか」が見えると、安心して口を開けやすくなります。 - 口を開けた瞬間に、さりげなく口腔内の様子も確認
異物残りや舌の動き、左右差などに気づけることも。気づかれないくらい自然にがポイントです。 - “全部してしまわない”ことが支援になる
スプーンを持つ手を添えるだけでも、自立支援につながることがあります。 - 言葉がけひとつで安心感が変わる
「ゆっくりで大丈夫ですよ」「おいしそうですね」「おいしいですか?」など、自然な声かけを意識しましょう。 - 違和感を覚えたときは、遠慮なく“チーム”に相談を
食事の姿勢に疑問を感じたらリハビリ職、食形態に不安を感じたら管理栄養士、
むせが多い・食事中にウトウトするなどの様子があれば看護師へ。
もちろん、近くにいる先輩や同僚と情報を共有することも大切です。 - 気づいたことは、そのまま介護記録へ
小さな変化や違和感も、あとで振り返れるよう記録に残しましょう。
記録は難しく考えず、見たまま・気づいたことを素直に書けば大丈夫。
よくある新人さんのつまずきと対策
| つまずき | 対策のコツ |
|---|---|
| スプーンを口の奥まで入れすぎてしまう | 唇に軽く触れたら、利用者の動きを待つ |
| 飲み込む前に次を出してしまう | 「ごっくん」を確認してから次の一口へ |
| むせた後すぐに再開してしまう | 一呼吸おいてから、少量を慎重に |
| 利用者の視界の外から口に運んでしまう | 口元が見える位置・下から運ぶ意識を |
| 口の中を見すぎて緊張させてしまう | 自然に・さりげなく観察する工夫を |
たけのこの一言🍀
食事介助って、技術よりも「その人をどう見てるか」が大事なんです。
相手の表情やペースを大切にすれば、自然といい介助になりますよ。


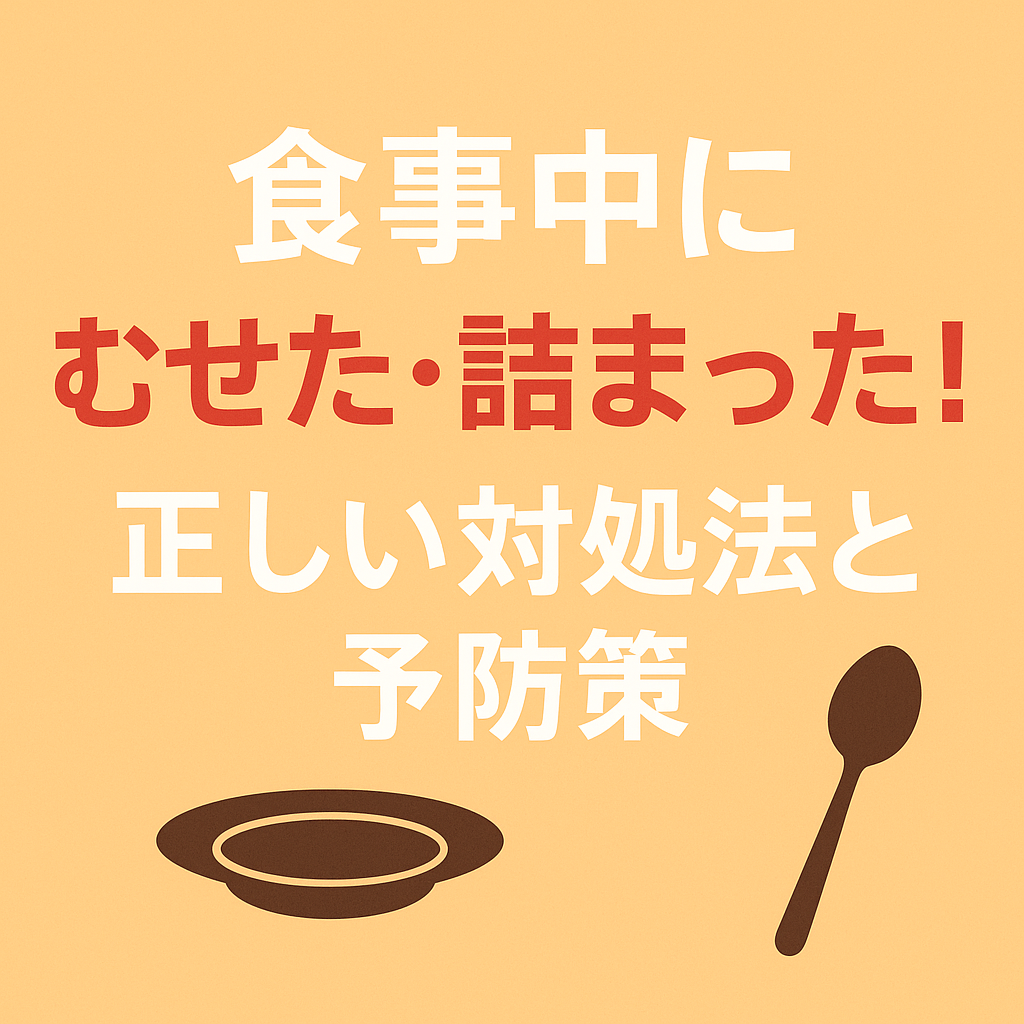
コメント