はじめに(新人の視点)
ある日、巡回中に転倒している利用者さんを見つけました。
「どうしよう、すぐ起こしていいのかな?それとも看護師を呼ぶべき?」
頭の中が真っ白になりかけたけど、先輩がそっと声をかけてくれて、冷静になれました。
今回は、新人の私が実際に学んだ「ケガ・転倒時の対応の基本」をまとめます。
焦らず、落ち着いて行動することが大切です。
1. ケガをしていた場合の対応
転倒時、出血や擦り傷、皮膚剥離などのケガがあることもあります。
まずは出血の有無と、傷の状態を確認します。
対応の基本:
- まずは手袋を着ける。血液感染を防ぐために必ず装着!
- 血が出ているときはガーゼや清潔なタオルで軽く押さえる(強く押しすぎない)
- 処置は看護師が行うため、すぐに報告する
- 服に血が付いていても脱がせない(傷が悪化することがある)
感染症予防も大切!
梅毒・肝炎などの血液を介した感染症のリスクもあるため、対応時は必ず手袋を着用。
手袋は常にポケットなどに予備を携帯しておくようにしています。
夜勤のときに困らないように…
夜勤中は看護師がいない(オンコール体制)ことが多いので、
昼間に看護師のケガ対応をしっかり見ておくことが大事です。
どこまで介護士が行って、どこから医療職に任せるのかを自分の目で見て覚えることが安心につながります。
2. 転倒を見つけたら、まずは観察+「人を呼ぶ」
- 駆け寄りたい気持ちをグッとこらえて、「観察」が先
- 意識はあるか? 出血はないか? どこを打っていそうか?
声かけをしながら観察する
「〇〇さん、どうしましたか?痛いところはありますか?」
そして“人を呼ぶ”!これが大事
状況をひとりで判断せず、すぐにナースコールや近くの職員を呼ぶ。
できれば一人は看護師を呼びに行き、一人は利用者さんのそばについて見守るのが理想です。
小さなケガでも、複数人で対応することで安全につながります。
「迷ったら、まずは呼んで。ひとりで抱え込まないことが大事だよ」
3. 勝手に起こさない!が鉄則
私は最初、手を引いて起こしそうになりました…
でも先輩に「頭や腰を打ってたら危ないよ」と止められました。
- 無理に起こさない
- 看護師の指示を待つ
- 体位を変えるのは医療職の判断があってから
4. 看護師や上司にすぐ報告
5W1Hでまとめて伝えるとスムーズ。
| 項目 | 内容の例 |
|---|---|
| いつ | ○時○分ごろ |
| どこで | 居室・トイレ・廊下など |
| だれが | 利用者の名前 |
| なにを | 転倒・すべった・ぶつけた…など |
| どうなったか | 頭を打った・痛がっている・出血あり |
| どうしたか | 看護師へ報告済・安静にしている など |
5. 記録で気をつけること
- 記録は正確に・事実のみ
- 見たこと、聞いたこと、した対応を順番に
- 勝手な予測は書かない(例:「多分○○だから…」)
転倒の状況(目撃の有無)や利用者の様子(訴え、痛み、出血など)、
看護師・家族への報告の有無と内容なども記録に残します。
6. ご家族への対応(施設マニュアルに沿って)
新人の私は基本的に直接対応はしませんでしたが、
家族に伝える内容が記録に残ることがあるので注意して見ておきました。
家族への説明は、看護師や上司が行うのが基本です。
対応の仕方は施設によって違うので、必ず施設のマニュアルや指示に従うことが大切です。
もし話を聞かれたら…
「詳しいことは看護師からご説明いたしますね」と落ち着いて答えるようにしています。
たけのこ流ひとこと
私も最初は転倒を見ただけでパニックでした。
でも先輩が「起こさなくていいよ。今は声をかけて観察だけでOK」と教えてくれました。
焦らず、命を守ることを最優先に行動すれば、ちゃんと伝わります!

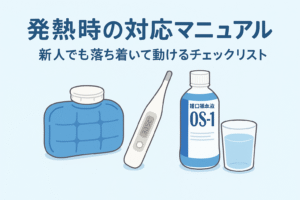

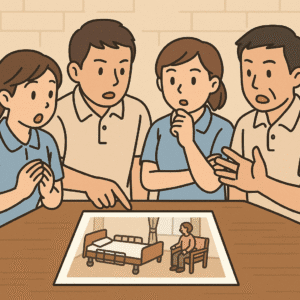
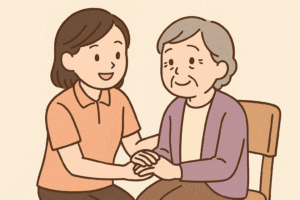
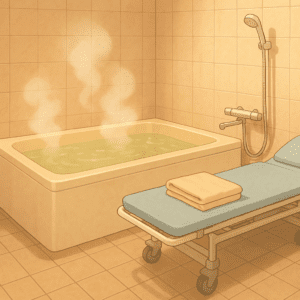
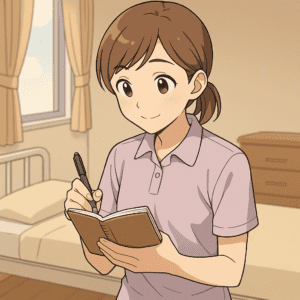
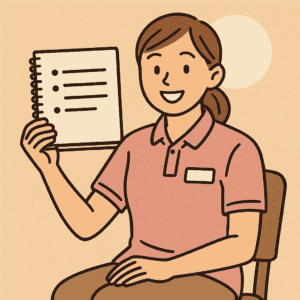
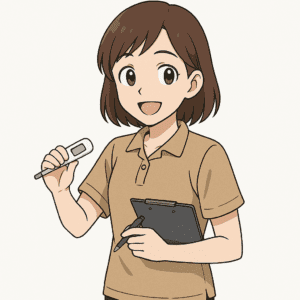
コメント