「初めての“記録”と、笑顔を引き出す“レク”。僕なりの工夫を見つけた日」
〇月〇日(〇)――八琉木みなぎの記録より
「今日のレク、八琉木みなぎくんが担当ね」
先輩の三谷さんにそう言われた瞬間、胸がドキドキしてきた。
レクを企画して進行するなんて、僕にできるのかな――。
初任者研修でレクリエーションの大切さは学んだけど、
現場では、まだ見学や準備係くらいしかしてこなかった。
でも今日は違う。
僕の名前が、堂々と「レク担当」に書かれていた。
間違い探し、手遊び歌、クイズ。
自分なりに工夫して準備して、ちょっと緊張しながらフロアに出た。
間違い探しでは、利用者さんがイラストをじっと見つめながら「これかな?」「いや、こっちも怪しいね」と話してくれて、僕はそのやり取りがなんだか嬉しかった。
手遊び歌では、ゆっくりとしたテンポで始めると、数人の方が自然に手を動かしてくれて、その動きに合わせて僕もリズムを取りながら声を出した。
クイズは季節の問題を用意していた。
「春の七草、全部言える人~?」と聞くと、「セリ、ナズナ……」と続けてくれた方がいて、周りから拍手が起きた。
少しずつ、場があたたまっていくのを感じた。
レクが終わって、少しホッとしたとき、三谷さんが言った。
「じゃあ、今日の記録、書いてみようか」
記録……?
そういえば、これまでちゃんと書いたことなかったかもしれない。
研修では習ったし、報告はしてたけど、“自分の言葉で残す”のは、初めてだった。
とりあえず書いてみた。
「○○さんは楽しそうだった。笑っていた」
三谷さんが、優しく声をかけてくれた。
「“楽しそう”は主観ね。誰が読んでもわかる“事実”を書くのが記録だよ」
“事実”って……なんだろう。
「たとえば“○○さんはクイズの答えを聞いて笑い、拍手をしていた”って書けば、様子が伝わるでしょ?」
なるほど。
感じたことじゃなくて、実際にあった行動や様子を書く。
それが記録なんだ。
三谷さんはさらに、こんなことも教えてくれた。
「記録って、家族から“見せてください”って言われたら、開示しなきゃいけないこともあるんだ」
「えっ、家族も見るんですか?」
「そう。だから、専門用語ばっかり使うと伝わらないことがあるの。
“ADLが向上した”より、“○○さんが今日はスプーンを自分で使って、完食していた”の方が家族に伝わるよね」
たしかに。
僕ももし家族が施設に入っていたら、「ちゃんと笑えてるのか」「元気にしてるのか」が知りたいと思う。
僕は書き直した。
「○○さんは間違い探しの紙を見て、笑いながら“これかな?”と発言。拍手をしながら答え合わせをしていた。」
記録って、介護士同士の連絡だけじゃなくて、
家族の安心にもつながるものなんだ。
少しだけ、“書く”ことが好きになれた気がした。
📌みなぎメモ(記録・観察の豆知識はこちら)
- 記録は「感想」じゃなくて「事実」を書く
✕ 楽しそうだった/◯ クイズの答えに笑って拍手していた - 誰が読んでも伝わるように、専門用語はできるだけ使わない
- 記録は、家族やチームみんなで“共有する言葉”という意識を持とう
🗒️みなぎの一言日記
「難しい言葉より、伝わる言葉。家族の安心につながる記録を書きたい。」
※この物語はフィクションですが、介護の現場で実際に起こり得るエピソードをもとに構成しています。
▶️← 第8話を読む
▶️八琉木みなぎシリーズまとめページへ
▶️第10話を読む →

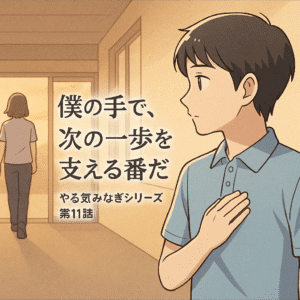

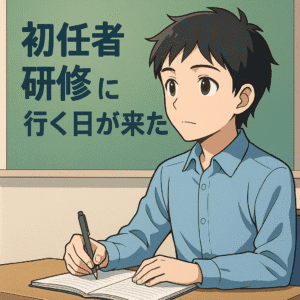
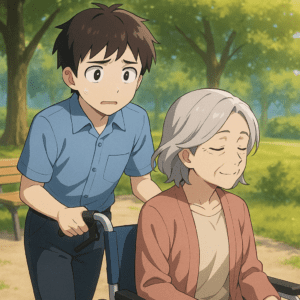
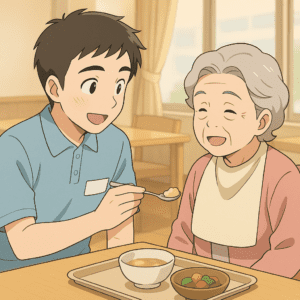

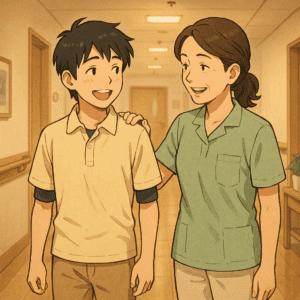
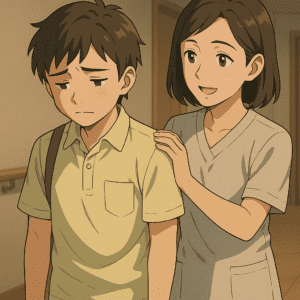
コメント