はじめに
「発熱=感染症」と思いがちですが、実はそうとは限りません。
脱水、疲労、薬の影響など、高齢者の体温はさまざまな理由で変化します。
この記事では、介護現場での「発熱そのもの」に焦点をあて、感染症かどうかまだ判断がつかない段階で、落ち着いて行動するための基本マニュアルをまとめています。
「どうすればいいの?」「様子を見るってなに?」と感じたとき、すぐに役立つ内容を集めました。
1. 発熱=すぐ感染症?その前に見るべきポイント
発熱=感染症と考えがちですが、それだけではありません。
- 脱水症状(例:水分摂取が少ない)
- 薬の副作用(抗がん剤、降圧剤など)
- 身体の疲労・ストレス
- 排尿や排便のトラブル
熱があると聞いたら、まずは「慌てず観察」から始めましょう。
2. 発熱時の初動チェックリスト
現場で最初に行うべき5つの行動:
- 体温を測定(耳式・脇式など正しく)
└ ※疑わしい場合は、時間を空けて2度行うこともあります。もちろん、利用者さんの苦痛にならないよう配慮しながら実施します。 - バイタルサインを確認(脈・血圧・呼吸・SpO₂)
- 水分摂取や食欲の有無を確認
- 顔色・発汗・動き・発言内容などの観察
- 記録を残し、看護師や先輩に報告・相談
※高齢者は自覚症状をうまく伝えられないこともあるため、「普段との違い」を意識して観察しましょう。
3. 「様子を見る」ってどういうこと?
報告後、「ちょっと様子を見てください」と言われることもあります。その場合は、次の点を意識します:
- 時間を決めて、再度バイタルを測る(例:30分後)
- 水分補給の声かけ(医師から制限がない場合)
└ ※スポーツドリンクや経口補水液(OS-1など)は、発熱時の水分・電解質補給におすすめです。無理なく飲めるものを提案しましょう。 - しんどそうであれば、なるべく横になってもらう
- 冷房や保温など、環境調整も忘れずに
高熱の出始めは寒気を感じやすいため、まずは保温が大切です。
その後、熱が上がりきってから暑さを訴える場合は、氷枕やエアコンの調整などを“様子を見ながら”行うのが基本です。
「様子を見る=何もしない」ではありません。観察を続け、「変化がないか」を注意深く見守ることが重要です。
4. 感染症が疑われるときとの違い
感染症が疑われる場合は、以下のような対応が必要です。
- 他の利用者への影響を考えて感染対策を取る
- マスク・手袋・動線の制限などを徹底
- 速やかに看護師・医師への報告と指示を仰ぐ
発熱の段階では、感染症かどうかの判断はつきません。
咳・下痢・嘔吐・倦怠感などの症状が出てきた時点で、感染対応に切り替えます。
5. 医療連携が必要になる判断のめやす
以下のような場合は、すぐに看護師や医師に連絡を取りましょう。
- 38℃以上の高熱
- SpO₂が90%以下に低下
- 意識がぼんやりしている、呼びかけに反応が鈍い
- 呼吸が荒い・苦しそう
- 嘔吐や下痢、咳がひどい
判断に迷ったら、すぐに相談。「おかしい」と思ったら伝えることが大切です。
6. まとめ|大切なのは“早めの気づき”と“落ち着いた対応”
- 観察→記録→報告→相談が基本
- 感染症かどうかは初期には分からない
- 様子を見るときも観察を継続する
不安になったときこそ、慌てず落ち着いて、できることから。
あなたの「気づき」が、利用者さんの安全につながります。
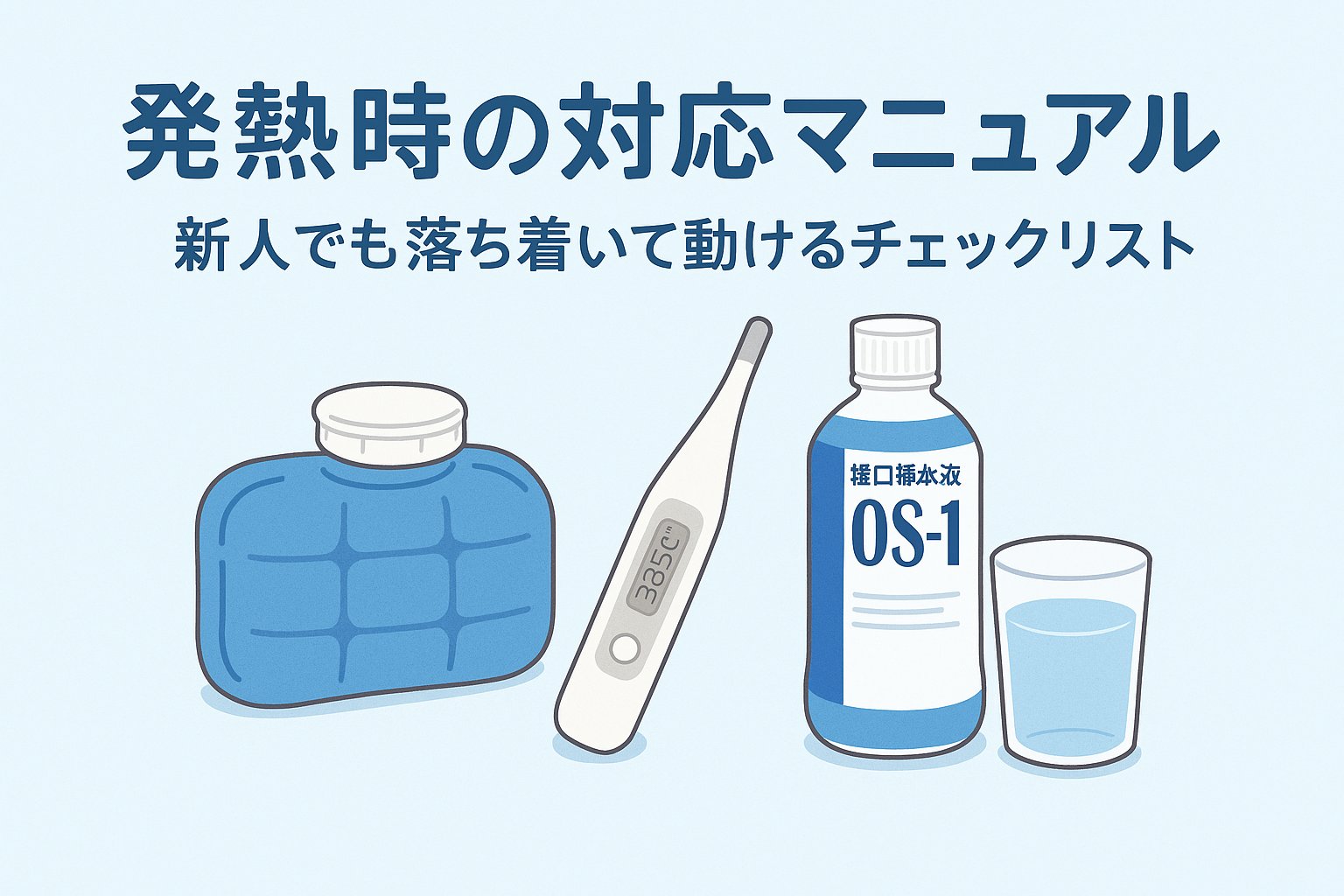
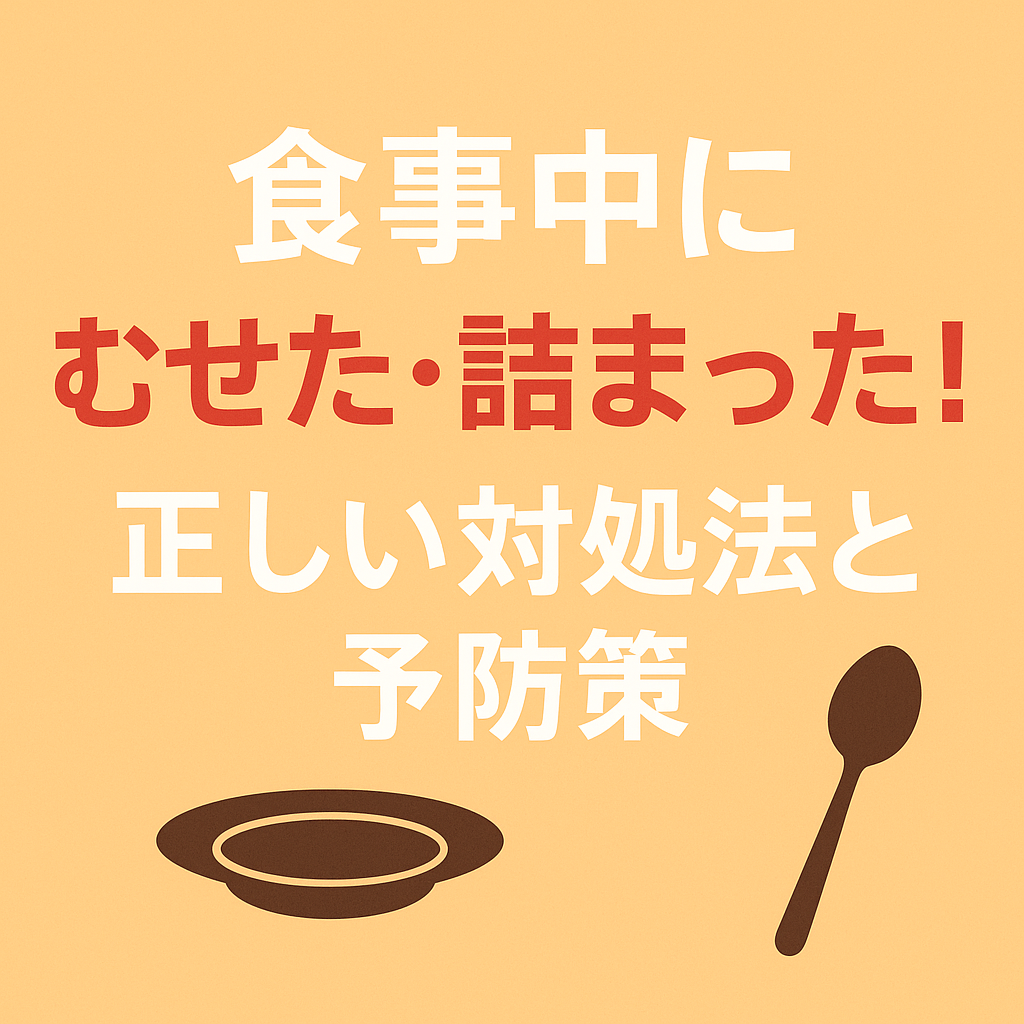
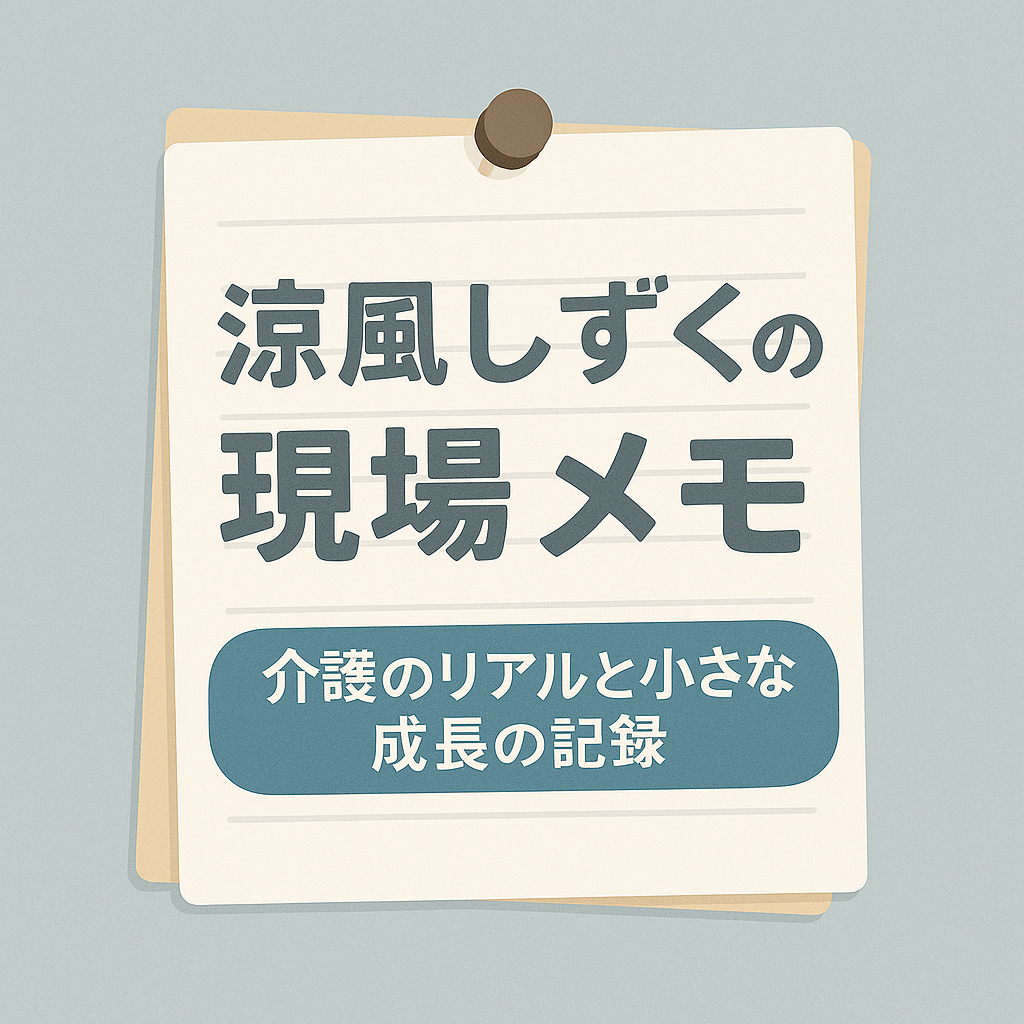
コメント