こんにちは、涼風しずくです。
現場では毎日、わからないことと出会います。
今回の“わからない”は、ちょっと怖かった。
食事介助中、利用者さんが突然むせてしまって——
しかも、かなり激しく。
「○○さん、大丈夫ですか!?」
私はスプーンを手にしたまま、立ち尽くしていた。
さっきまで穏やかに食べていた○○さんが、咳き込みながら苦しそうに顔をしかめていた。
(え…私のせい?)
何が起きたのか、頭が真っ白だった。
急いで先輩が近くに駆け寄ってきて、○○さんの背中をさすりながら声をかける。
私は何もできず、ただ呆然としていた。
“むせる”って、こういうことだったんだ。
今まで、“ちょっと咳き込む”くらいに思ってた。
でも違った。もっと急で、もっと怖くて、そして……
なによりも、自分が原因かもしれないって思ったとき、足がすくんだ。
その日の帰り道、私はコンビニでプリンを買って、それを見つめながらスマホを開いた。
(「とろみ」「むせ」「食事介助 失敗」……)
検索欄に並んだワードが、いまの私の不安そのままだった。
いろんな記事を読んでみたけど、頭の中は「私が悪かったのかな」でいっぱいだった。
翌朝、勇気を出して、先輩の宮本さんに声をかけた。
「昨日、○○さんがむせちゃって…私、何か間違ってたんでしょうか」
「そうね、あの場面だけじゃ判断しづらいけど——」
「ひと口の量、ちょっと多かったかもね」
あ…。確かに、少しスプーンにすくいすぎたかもしれない。
昨日の○○さん、口を開けたあと、少し戸惑ってたような気もする。
「あとね、とろみの量は、栄養士さんや看護師さんが調整してくれてるから、基本はそのままで大丈夫よ。
ただ、汁物は流れやすいから、ひと口の量とかスピードには気をつけてね」
少し沈黙してしまった私に、宮本さんがやさしく続けた。
「食事介助ってね、最初は誰でも緊張するものなの」
「でも、だんだん慣れてくるから。あんまり自分を責めすぎないでね」
その言葉に、心の中の張りつめていたものが、少し緩んだ気がした。
その日の夜、私は改めてスマホで「むせにくい食事介助」を検索した。
いろんなサイトを見ていると、共通して書かれていたのは——
- 姿勢:背筋を伸ばして、やや前傾。顎は自然な位置で。
- 声かけ:「ゆっくりで大丈夫ですよ」「飲み込めましたか?」など穏やかに確認。
- 焦らない:飲み込む前に次を運ばない。
そして、ある言葉が目に留まった。
「むせは、起きるときには起きます。大事なのは、その後どう対応するかです」
(…なんだか、少し気が楽になった気がした)
翌日の食事介助。私は昨日のことを思い出しながら、慎重にスプーンを運んだ。
量は少なめ。
○○さんの目線に合わせて、ゆっくりと。
ひと口ごとに、飲み込んだのを確認してから次をすくう。
「ごちそうさまでした」
○○さんの穏やかな声に、私はようやく深く息を吐いた。
“むせさせちゃった”ことは、私の中で忘れちゃいけない出来事。
でも、それがあったから今、“気をつけること”がちゃんと見えた気がする。
📒しずくの現場メモ
- 一口量は少なめに
- 飲み込んだか確認してから次へ
- 汁物はとろみの有無をチェック
- やや前傾姿勢を整える(背もたれに寄りかからせない)
- 声かけで本人の反応を見る
- とにかく、焦らないこと
- むせは起きることもある。その後の対応が大事
合わせて読みたい記事
- ✅ 新人介護士さんへ|はじめての食事介助で気をつけたいこと
→ 食事介助の基本をわかりやすくまとめた解説記事です - ✅食事介助中に「むせた・詰まった」時の正しい対処法と予防策
→ むせの原因と正しい対応・予防を知っておこう!
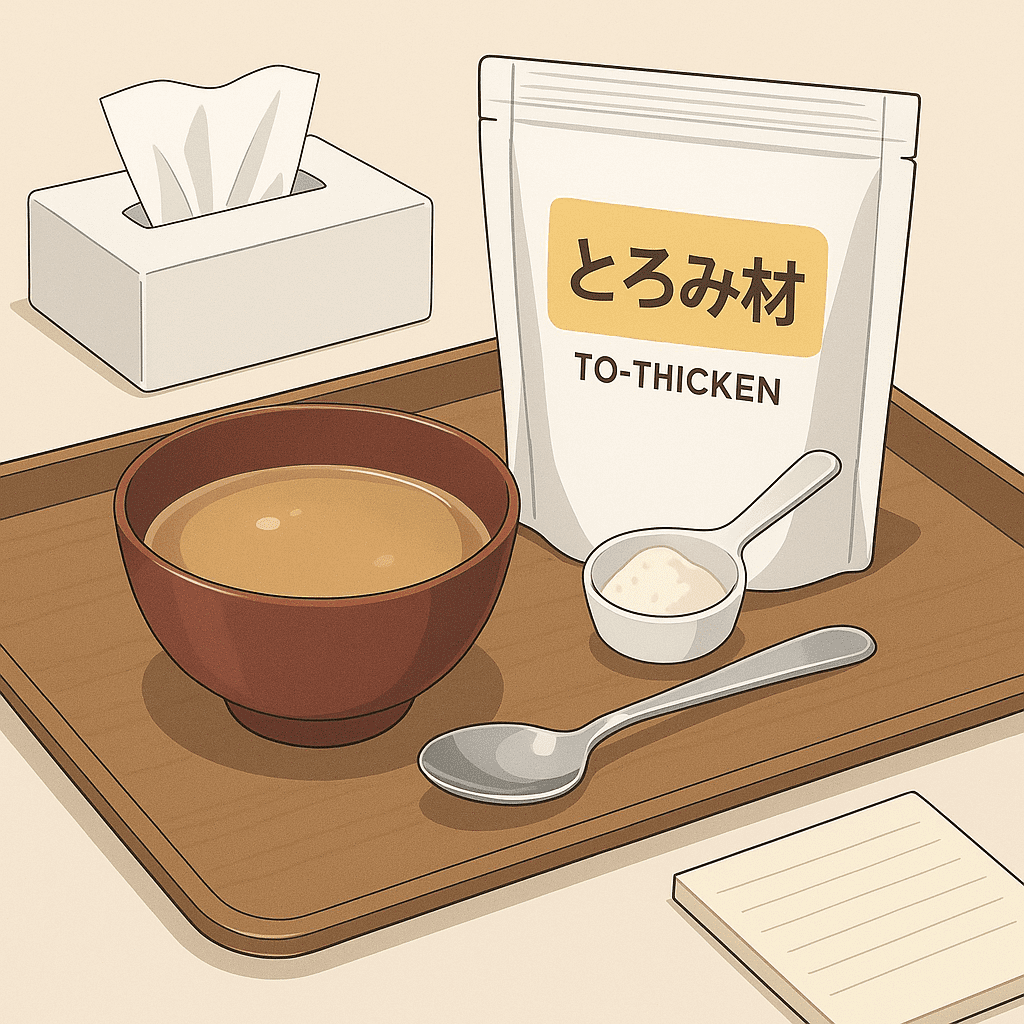
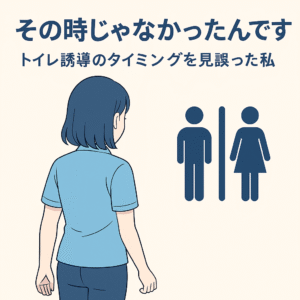
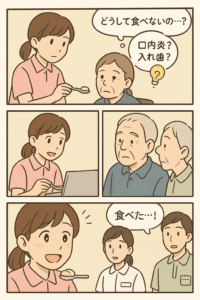

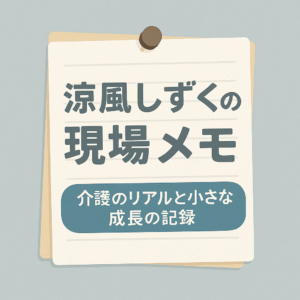
コメント