「“ありがとう”の重み。食事介助、僕にできること」
📅 4月11日(木)/☁️→☀️ 少し肌寒い朝
導入
「みなぎくん、今日は○○さんの食事介助お願いね」
朝の申し送りで先輩から声をかけられた瞬間、
胸の奥に、ズンと重いものが落ちてきた。
――ついに来たか、食事介助。
入浴のときとは、また違う緊張が押し寄せる。
人が“生きる”ために欠かせない「食事」。
それをサポートするというのは、簡単じゃない。
「むせさせたら?」「飲み込みづらそうだったら?」「口、開けてくれなかったら?」
そんな“もしも”が、頭の中をぐるぐる回っていた。
利用者さんにとって食事は、楽しみでもあり、命そのものでもある。
その時間を壊してしまったら――
そんな怖さが、ずっとつきまとっていた。
展開
昼食の時間。
配膳カートの湯気が、ホールの空気をほんのり温める。
お盆の上には、やわらかい煮物、ごはん、そしてとろみ付きのすまし汁。
どれも香りがよくて、思わず自分もお腹が鳴りそうになる。
でも、そんな余裕はなかった。
「◯◯さん、こんにちは。今日も一緒に、いただきましょうね」
なんとか声を出したけど、どこかぎこちない。
みなぎが座った正面には、優しそうな目をした○○さん。
けれど、その口元はピクリとも動かない。
スプーンを持った手が、わずかに震える。
(あれ…? 口を開けてくれない)
時間だけが過ぎていく。
他のテーブルでは、「美味しいねぇ」「そのおかず、好きなんよ」と
和やかな会話が広がっているのに、自分だけが取り残された気分だった。
(やっぱり僕にはまだ早かったんじゃ…)
自信が音を立てて崩れていきそうなとき――
「みなぎくん、大丈夫?」
背後から、先輩の穏やかな声。
「○○さんは、最初ちょっと人見知りだけど、
ゆっくり声かけすると、ちゃんと応えてくれる人だよ」
「タイミング、焦らなくていいよ。一緒にやってみよう」
すっと隣に座る先輩。
その存在に、ふっと肩の力が抜けた。
クライマックス
「○○さん、これ、柔らかいおかずですよ。お口に合うと思います」
みなぎは、スプーンを一度見つめ、
(口の下から、目で見えるところから運ぶんだったよな…)
と心の中で確認してから、そっと差し出した。
ほんの数秒の沈黙のあと、
○○さんが、ゆっくりと口を開けた。
その瞬間、心の中で何かが「パチン」と弾けたようだった。
――食べてくれた。
みなぎは、じっと○○さんの口元と喉に視線を向ける。
(飲み込んだ…うん、大丈夫)
次のひと口をゆっくりと準備する。
「ありがとうねぇ、美味しかったわ」
○○さんが微笑んだその顔は、どこか誇らしげだった。
みなぎは、胸の奥がじわっと熱くなるのを感じた。
ラスト
ロッカー室で着替えながら、みなぎはさっきの「ありがとう」を思い出していた。
介護って、ただお世話をする仕事じゃない。
その人がその人らしくいられるように、
日々の“当たり前”を支えることなんだ。
食事介助。
それは、「口に運ぶ」以上に、
“心に寄り添う”ということ。
今日、少しだけその意味がわかった気がした。
✅ みなぎの一言日記
「たった一口。けれど、その一口にこめた想いが、伝わった気がする。介護って…深いな。」
📘 みなぎメモ
- 食事介助では“焦らない・無理させない”が鉄則
- しっかり“飲み込んだのを確認”してから、次のひと口を運ぶ
- スプーンは、利用者さんの“視界の中”で動かす(口の下から・目線の位置)
- むせたときは無理に続けず、落ち着いてから“少量で再開”して様子を見る
- 声かけや表情で、安心感を伝えることが大事
- 食べてくれる=信頼の証
- 「ありがとう」は、介護職にとって最高のご褒美
📚 やる気みなぎシリーズ 関連リンク
※この物語はフィクションです。登場する人物・団体・エピソードはすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
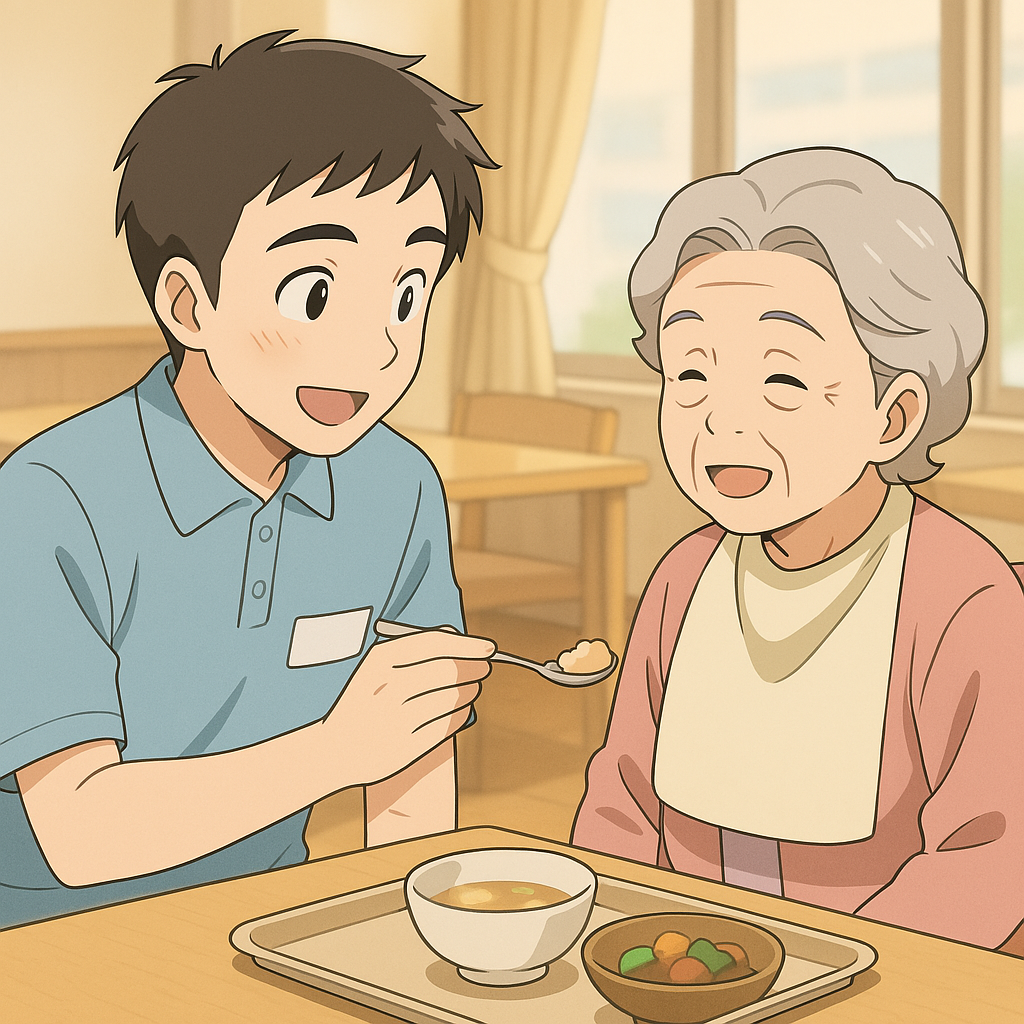
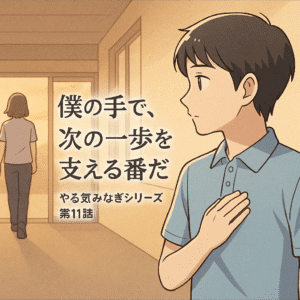


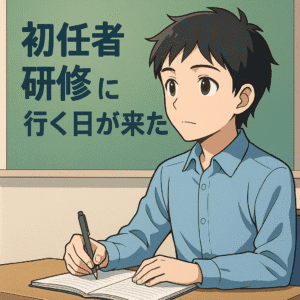
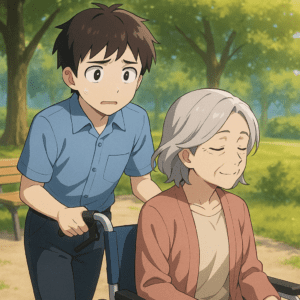

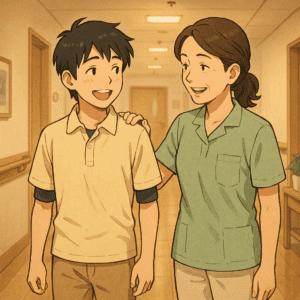
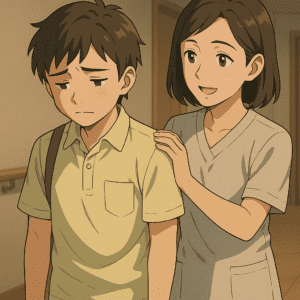
コメント