『“介護過程”って、こんなに深かったんだ。』
〜 現場1年目を超えて見えてきた、“考える介護”のむずかしさ 〜
こんにちは、みなぎです。
介護の現場に入って、1年と少し。
できることも増えて、「新人」と呼ばれることは少なくなってきた。
どこかで「自分はもう一人前だ」と思っていたのかもしれない。
その慢心を最初に打ち砕いてくれたのが、実務者研修だった。
📚 「介護過程」と向き合う日が来た
実務者研修の初日、教室に入った瞬間に空気の違いを感じた。
年上の受講者も多く、現場経験もバラバラ。
緊張している人もいれば、余裕のある表情の人もいた。
講師の先生が最初に言った言葉が印象に残っている。
「この研修は、“ただの技術者”から、“考える介護士”になるための学びです。」
黒板に書かれた「介護過程」という文字は見慣れなかったけど、その重みはひしひしと伝わってきた。
💡 ワークで気づいた、自分の限界
講義の途中で出されたワークは、次のようなものだった。
「Aさん(85歳・女性)が最近、ご飯を食べ残すようになった理由を、情報から導いてください。」
配布されたシートには、体調の変化や生活歴、発言記録などが詳しく載っていた。
自信があった僕は、「年齢の影響で食欲にムラがあるのでは」と答えた。
そのとき、講師が笑いながらこう言った。
「それは“あなたの想像”ですよね。根拠はありますか? どんな情報を見て、どう判断したのですか?」
その一言が胸に刺さった。
僕はこれまで、なんとなくの経験則で介護をしていた。
目の前の様子から「きっとこうだろう」と判断して行動してきた。
でも、それは本当に“理解”に基づいた支援だったのか、自問せざるを得なかった。
🔍 現場で流していたことを深く考える
グループワークでは、別の施設の職員がこう言っていた。
「Aさんは最近、人との会話が減っています。独居生活が長く、施設に入ったばかりなので、環境の変化によるストレスもあるのではないかと感じました。」
その人は、観察記録にある表情や発言、居室での様子まで細かく読み取って、そこから心理的な変化を丁寧に推測していた。
正直、僕はそこまで見ていなかった。
「何をすべきか」ばかりに目が向いていて、「なぜそうなったか」という視点を持てていなかったことに気づいた。
🔄 午後の講義:医療的ケアの衝撃
午後の講義は、医療的ケアだった。
たん吸引や経管栄養など、これまで「看護師の仕事」として遠ざけていた領域だった。
講師の先生は、こんな言葉で講義を始めた。
「制度上、条件を満たせば介護士も医療的ケアを行えます。大切なのは、やり方だけでなく“なぜ行うのか”を理解することです。」
教材に載っていたチューブや吸引機、トロミ調整などが実物として目の前に現れ、息をのんだ。
「命に関わるケアだからこそ、“やれる”ではなく、“任せてもらえる”人になってください。」
その言葉が、今も強く心に残っている。
🪴 “考える介護”の一歩を踏み出す
講義が終わる頃には、頭がいっぱいだった。
正直、悔しさもあった。
でもそれと同時に、「もっと学びたい」と心の底から思った。
休憩時間に、同じ班の受講者が言った言葉が印象的だった。
「現場では忙しくて、ついパターンで動いてしまう。でもそれって、相手の気持ちを置き去りにしていることもあるよね。」
その通りだと思った。
実務者研修は、“やり方”を学ぶ場ではなく、“考え方”を見直す場だった。
✏️ みなぎの一言日記
なんとなくでやっていた自分に、今日、はじめてちゃんと向き合った。
でもそれは、変わるチャンスでもあると感じている。
命に関わるケアとも、ちゃんと向き合いたい。
📌 みなぎメモ(豆知識)
実務者研修とは?
・初任者研修の上位資格で、介護福祉士の受験要件にもなる
・介護過程(アセスメント・計画・実施・評価)を本格的に学ぶ
・たん吸引・経管栄養などの医療的ケアの基礎を学べる
⬅️ 【前話】
カフェの帰り道、語った僕の“ヒヤリ”|第5話
➡️ 【次話】(次話公開後にリンク設置予定)
📚 【まとめ】
やる気みなぎ【奮闘日記】まとめページはこちら
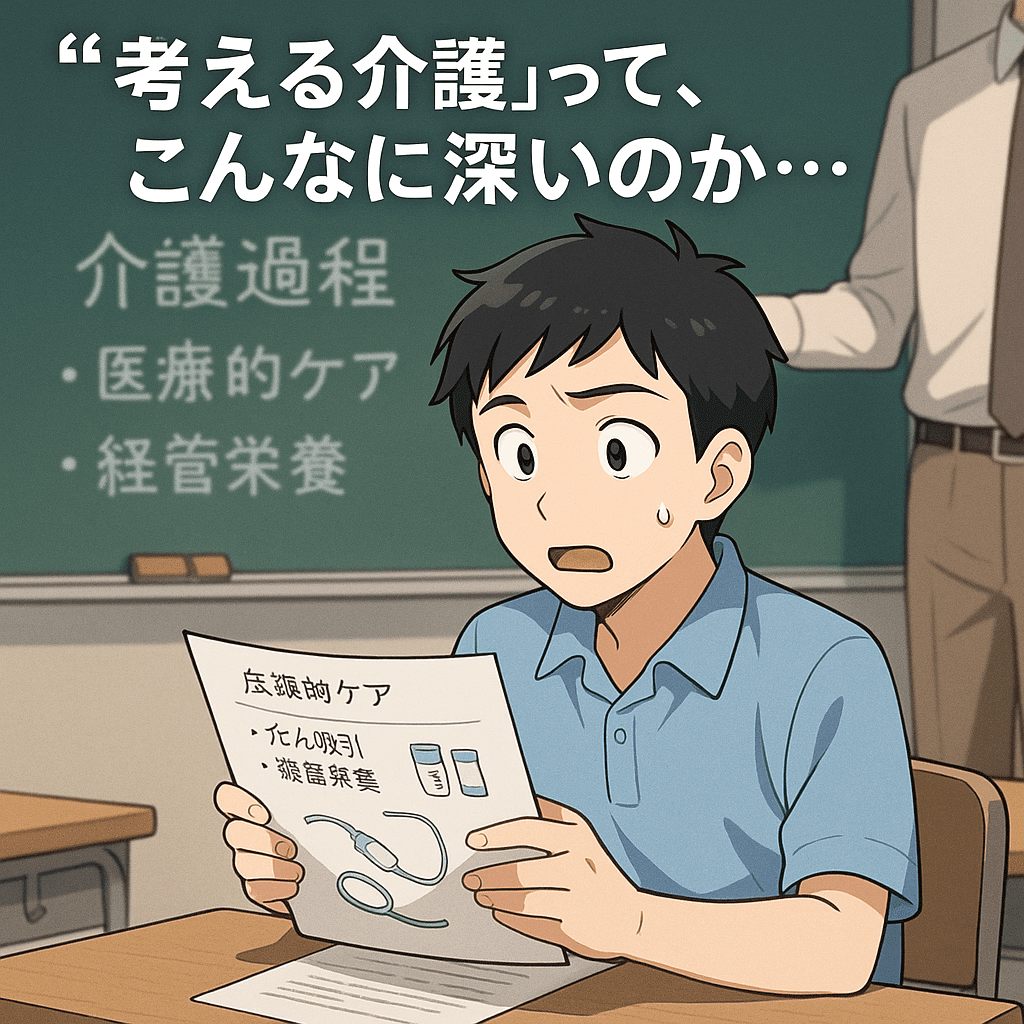

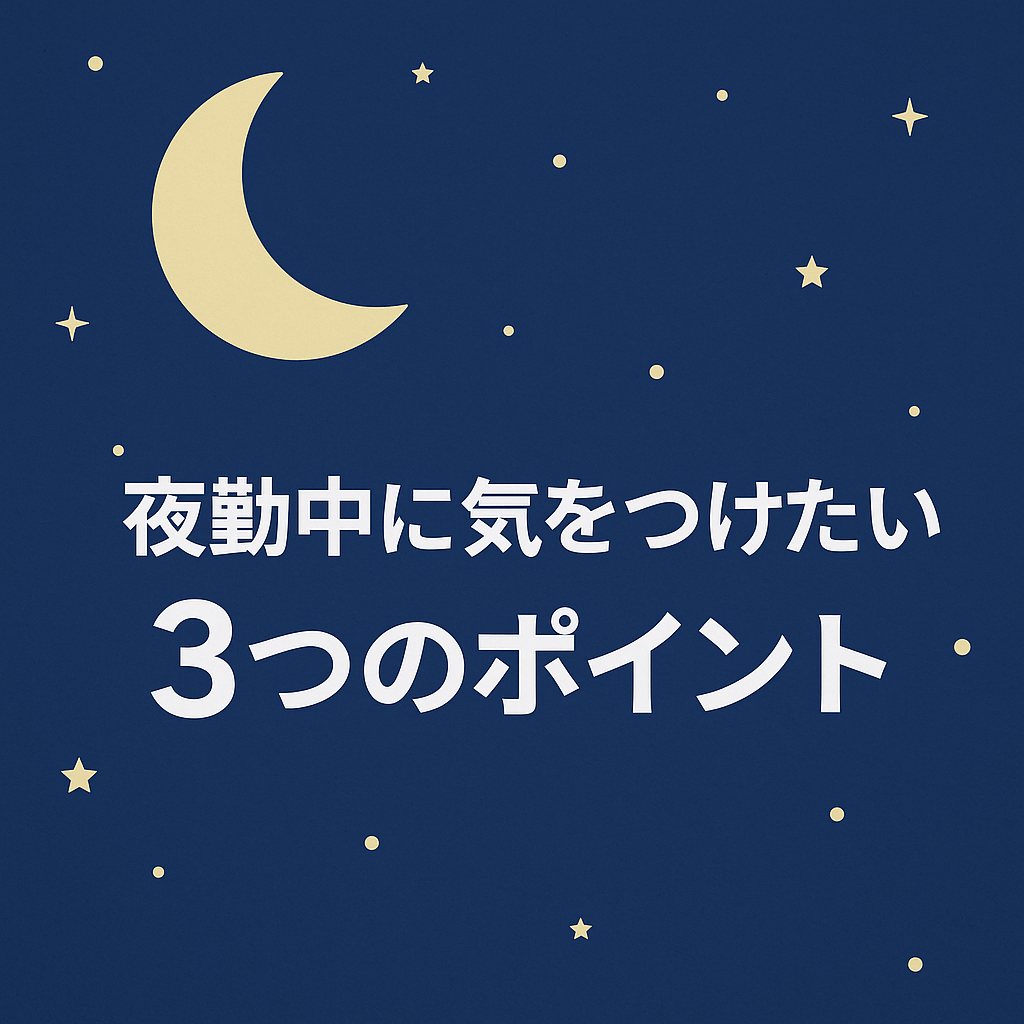
コメント